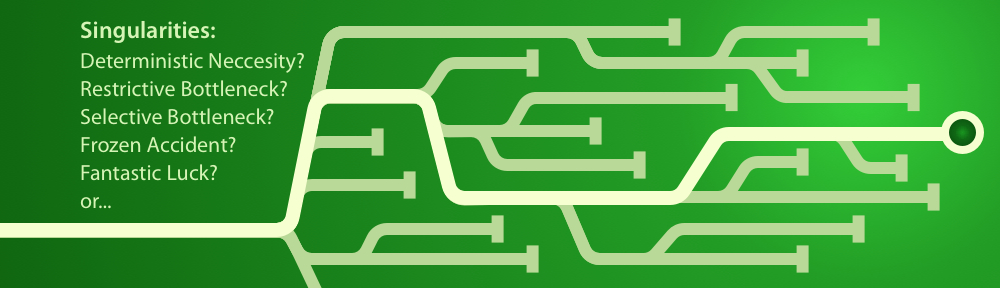科学者たちは実験のことを時に「美しい」と形容する。ぼく自身も科学者の端くれだが、確かにそうだ。美しい実験、美しい結果といった言葉づかいに違和感はない。著者は、哲学者・科学史家という自分の立ち位置から、科学者たちとの対話を通して、その「美しさ」の意味をくみ取り、10の「美しい科学実験」を通して、「実験にとって美しさの意味とは何か」「実験に美しさがあるのなら、それは美にとって何の意味があるのか」という2つの問いに答えようとする。もともとは雑誌「Physics World」での連載であり、取り上げられた10の実験はアンケートに基づいて選ばれている。おそらく実験とは、科学者にとって自分自身との対話であり、自分自身の哲学が具現する瞬間でもある。だから、実験を経た後の科学者の言葉は、その深さと重さを増す。訳者もあとがきに書いているが、ニュートンの「光は屈折するときにその色を変えない」という言明に、この書物の中で出逢うとき、理性ではなく感性を揺さぶられ、涙すらあふれてくる。科学が、芸術同様に人間の感性に訴えかける営みであることを著すことに、著者は成功している。10の実験について語った各章を結ぶ間章もとても興味深い。
科学者たちは実験のことを時に「美しい」と形容する。ぼく自身も科学者の端くれだが、確かにそうだ。美しい実験、美しい結果といった言葉づかいに違和感はない。著者は、哲学者・科学史家という自分の立ち位置から、科学者たちとの対話を通して、その「美しさ」の意味をくみ取り、10の「美しい科学実験」を通して、「実験にとって美しさの意味とは何か」「実験に美しさがあるのなら、それは美にとって何の意味があるのか」という2つの問いに答えようとする。もともとは雑誌「Physics World」での連載であり、取り上げられた10の実験はアンケートに基づいて選ばれている。おそらく実験とは、科学者にとって自分自身との対話であり、自分自身の哲学が具現する瞬間でもある。だから、実験を経た後の科学者の言葉は、その深さと重さを増す。訳者もあとがきに書いているが、ニュートンの「光は屈折するときにその色を変えない」という言明に、この書物の中で出逢うとき、理性ではなく感性を揺さぶられ、涙すらあふれてくる。科学が、芸術同様に人間の感性に訴えかける営みであることを著すことに、著者は成功している。10の実験について語った各章を結ぶ間章もとても興味深い。
SYNC
 いっせいに明滅するホタルなど、印象的な同期現象を導入として、前半は、社会といったマクロスケールから、細胞といったミクロスケールにわたり普遍的に見られる同期現象と、その背後に存在するかもしれない共通の原理について物語られる。後半は、同期現象から徐々に話題を拡大し、カオスやネットワーク科学といった、現代の非線形科学全般へと話題が及んでいく。エピソードの選び方と語り口が見事なため、何となく読んでいると、いつのまに話題が同期現象を離れ、いつのまにまた同期現象とつながってきたのか気づかないほどである。還元主義に偏りすぎた現代自然科学への批判的な視線が随所に現れるのもおもしろい。ストロガッツほどの科学者が、自分を「主流」とは考えていないのだ。
いっせいに明滅するホタルなど、印象的な同期現象を導入として、前半は、社会といったマクロスケールから、細胞といったミクロスケールにわたり普遍的に見られる同期現象と、その背後に存在するかもしれない共通の原理について物語られる。後半は、同期現象から徐々に話題を拡大し、カオスやネットワーク科学といった、現代の非線形科学全般へと話題が及んでいく。エピソードの選び方と語り口が見事なため、何となく読んでいると、いつのまに話題が同期現象を離れ、いつのまにまた同期現象とつながってきたのか気づかないほどである。還元主義に偏りすぎた現代自然科学への批判的な視線が随所に現れるのもおもしろい。ストロガッツほどの科学者が、自分を「主流」とは考えていないのだ。
ポピュラーフィクションとして一級品(一部、専門用語に誤訳があるのが残念)。
脳のなかの水分子—意識が創られるとき
 「いち・たす・いち」「ぷらす・あるふぁ」につづく、中田力教授の「脳の渦理論」第3作。複雑系科学を俯瞰する「いち・たす・いち」、脳の渦理論の確信を描く「ぷらす・あるふぁ」に対して、本書は、筆者がこの理論へと至った背景が綴られている。
「いち・たす・いち」「ぷらす・あるふぁ」につづく、中田力教授の「脳の渦理論」第3作。複雑系科学を俯瞰する「いち・たす・いち」、脳の渦理論の確信を描く「ぷらす・あるふぁ」に対して、本書は、筆者がこの理論へと至った背景が綴られている。
ライナス・ポーリングへの畏敬の念が全編にわたって語られ、同時に科学界というコミュニティへの心情も強く吐露されている。科学という営みも人間の手によりなるものである以上、完全な「公正」はありえない。その中で、いかに科学的真理を求めるのか、を自然科学者ひとりひとりが考えなければならないわけだが、現在は、そもそもそうした視座に到達する研究者自体が限られている状況にある。筆者自身が渦理論をどう携えていこうかと試行錯誤するようすは、ある意味理不尽ではあるが、科学者として至極真っ当な懊悩と受け取った。
「いち・たす・いち」「ぷらす・あるふぁ」と本書を再編して、1冊にまとめた作品を読みたいと思う。そうした形で読まれた方がおそらくは幸福な書物ではなかろうか。
人類が知っていることすべての短い歴史
 私たち=人類がこの星に誕生するに至るまでに、この宇宙ではいったい何があったのか。科学者たちはどうやってそれを明らかにしてきたのか。ビル・ブライソンは門外漢ならではの大胆さで科学の奥座敷にドカドカと踏みいり、見て感じたとおりに「科学」という営みを描く。描きだされるのは、科学者という滑稽な人々が織りなす低俗な争いと、荘厳な知識のタペストリ。圧倒的におもしろい。
私たち=人類がこの星に誕生するに至るまでに、この宇宙ではいったい何があったのか。科学者たちはどうやってそれを明らかにしてきたのか。ビル・ブライソンは門外漢ならではの大胆さで科学の奥座敷にドカドカと踏みいり、見て感じたとおりに「科学」という営みを描く。描きだされるのは、科学者という滑稽な人々が織りなす低俗な争いと、荘厳な知識のタペストリ。圧倒的におもしろい。
本書は科学史に軸足を置いており、科学的知識そのものの説明はかなり表層的に端折られている。これを読んで何かを「理解した」とは思えないだろう。作者自身も、最近100年の科学を「ほとんどの人が何ひとつ理解できない」と書いている。ごまかしや誤りを書き連ねるくらいなら、そもそも書かない、というのはむしろ潔い。科学的知識を学びたいのなら、アトキンスやマット・リドレーなど、科学者あるいはサイエンス・ライタによる著作に如くものはないだろう。
一方で、科学を生業としない「一般人」の目で作者が科学を見渡し、本書の内容として選び取った領域を眺めてみるのも興味深い。ぼくは生物学に携わる研究者の端くれだが、本書の後半を占める生命科学で描かれるトピックは、現代生命科学の王道とはかなりズレている。これをビル・ブライソンの偏見とみるか、それとも、生命科学という営みがボタンを掛け違えつつあるのか、考えさせられる。
数理生理学

原書は米国出版協会の「Best Mathematics book of 1998」を受賞した良書。実際、酵素反応速度論や電気生理の基礎から、視覚、消化吸収、循環などの高次現象までを幅広くおさえた、数理にも生理にも偏らない、真っ向「数理生理学」の教科書であり、他に類をみない本である。ただし、和訳は必ずしも優れているとはいえない。散見される読みにくさ、専門用語の誤訳などには目をつぶるとしても、文章やパラグラフがまるごと訳されていなかったりする部分もあり、さすがにいかがなものかと思う。原書を脇に置きつつ読み進めることをオススメする。

和訳では「システム生理学」のサブタイトルが付けられているが、その内容は、巨視的(macroscopic)な現象の数理生理学である。上巻で言及された微視的(microscopic)な現象のモデルを活用しつつ、循環や腎での尿生成、消化吸収、視覚、聴覚などの複雑だが身近な現象のモデリングと議論が展開される。難解な部分も多いが、数学を用いることで生命科学がいかに深まるか、そのポテンシャルを体感できる。上巻同様、翻訳には難あり。内容だけなら5つ☆の良書。
自然の中に隠された数学
 物理学を筆頭とする従来の要素還元型の自然科学で取り扱うのが難しい問題がある。そういった問題の一部に対して、複雑系科学をはじめとする非線形科学が有効かもしれない。本書では、カオス理論や複雑系科学によって、これまでの自然科学が上手に取り扱うことができなかった、形やパターンが生まれる仕組みが解き明かされていく様子が描きだされていく。その積み重ねによって、非線形科学の有効性が腑に落ちるように仕掛けられている。本書の内容に魅惑されたなら、スチュアートの他の著作をはじめとした書物に手を伸ばすきっかけを捕まえたといえる。入門書の中の入門書。次の1冊としてはスチュアート「生命に隠された秘密」あたりがオススメ。
物理学を筆頭とする従来の要素還元型の自然科学で取り扱うのが難しい問題がある。そういった問題の一部に対して、複雑系科学をはじめとする非線形科学が有効かもしれない。本書では、カオス理論や複雑系科学によって、これまでの自然科学が上手に取り扱うことができなかった、形やパターンが生まれる仕組みが解き明かされていく様子が描きだされていく。その積み重ねによって、非線形科学の有効性が腑に落ちるように仕掛けられている。本書の内容に魅惑されたなら、スチュアートの他の著作をはじめとした書物に手を伸ばすきっかけを捕まえたといえる。入門書の中の入門書。次の1冊としてはスチュアート「生命に隠された秘密」あたりがオススメ。
新しい自然学
科学哲学の冒険
実例で学ぶ医学英語論文の構成技法
 本書は、UCSFでの科学論文作法の授業から生まれた教科書で、英語を母国語とする若手研究者のためのものだが、日本人研究者にもものすごく役に立つ。第1部では、単語の選び方、文の構造、パラグラフの構造について、良い文章を書くためにどう考えるのかが論理的に示される。第2部では、論文を構成する序論、材料と方法、結果、議論の各ブロックに、何をどういった順序で書くべきであり、また何を書いてはいけないのかが、明確に理由付けされて著されている。
本書は、UCSFでの科学論文作法の授業から生まれた教科書で、英語を母国語とする若手研究者のためのものだが、日本人研究者にもものすごく役に立つ。第1部では、単語の選び方、文の構造、パラグラフの構造について、良い文章を書くためにどう考えるのかが論理的に示される。第2部では、論文を構成する序論、材料と方法、結果、議論の各ブロックに、何をどういった順序で書くべきであり、また何を書いてはいけないのかが、明確に理由付けされて著されている。
また、全編にわたり若手研究者の論文草稿が「例題」として示され、どう改善することでよりよい論文になるのかが具体的に示される。
科学論文をどう構成してよいのかについて迷いのある人は、是非本書を眺めてほしい。何かしらのヒントを得られるはずだ。
(原書は2000年に第2版が出版され、図表のまとめ方などに関するレクチャーが追加されている)
ガリレオの指
 科学に興味を持つ大学生、高校生に是非読んでもらいたい。若者の人生を変えるポテンシャルを持ったすばらしいポピュラーサイエンス。アトキンスの数々の著作の中でも、際だった傑作。
科学に興味を持つ大学生、高校生に是非読んでもらいたい。若者の人生を変えるポテンシャルを持ったすばらしいポピュラーサイエンス。アトキンスの数々の著作の中でも、際だった傑作。
科学的に世界を眺めるためのヒントが全巻にわたって横溢している。全体の構成、構想が凄い。進化、DNA、エネルギー、エントロピー、原子、対称性、量子、宇宙論、時空、算術。さまざまな話題を往還しつつ、大局的には、身近なものから人間の知覚スケールとは乖離したものへ、具体的なものから抽象的なものへと読者を導いていく、この全体構成の企みの大胆さ。それを実現してしまう膨大な知識。
人間は、抽象的な概念操作を無理なくこなせる不思議な動物だが、最終章「算術」に至って、数を数えられる、ということの不思議さが実感をもって迫ってきて、身震いする。この世界、そしてこの世界の一員であるぼく自身の存在の不思議さ、おもしろさを存分に味わわせてくれる。