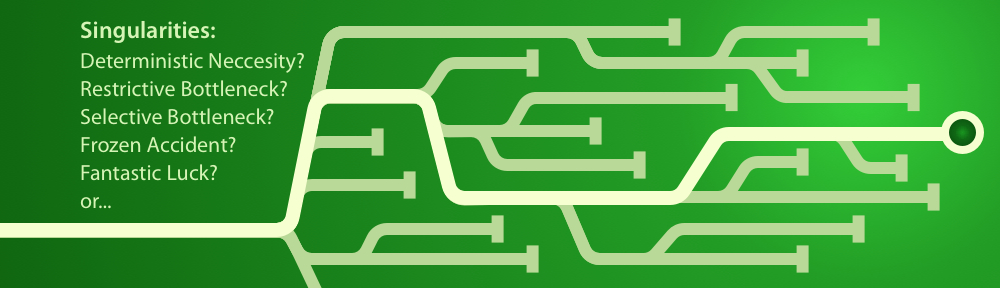私たち=人類がこの星に誕生するに至るまでに、この宇宙ではいったい何があったのか。科学者たちはどうやってそれを明らかにしてきたのか。ビル・ブライソンは門外漢ならではの大胆さで科学の奥座敷にドカドカと踏みいり、見て感じたとおりに「科学」という営みを描く。描きだされるのは、科学者という滑稽な人々が織りなす低俗な争いと、荘厳な知識のタペストリ。圧倒的におもしろい。
私たち=人類がこの星に誕生するに至るまでに、この宇宙ではいったい何があったのか。科学者たちはどうやってそれを明らかにしてきたのか。ビル・ブライソンは門外漢ならではの大胆さで科学の奥座敷にドカドカと踏みいり、見て感じたとおりに「科学」という営みを描く。描きだされるのは、科学者という滑稽な人々が織りなす低俗な争いと、荘厳な知識のタペストリ。圧倒的におもしろい。
本書は科学史に軸足を置いており、科学的知識そのものの説明はかなり表層的に端折られている。これを読んで何かを「理解した」とは思えないだろう。作者自身も、最近100年の科学を「ほとんどの人が何ひとつ理解できない」と書いている。ごまかしや誤りを書き連ねるくらいなら、そもそも書かない、というのはむしろ潔い。科学的知識を学びたいのなら、アトキンスやマット・リドレーなど、科学者あるいはサイエンス・ライタによる著作に如くものはないだろう。
一方で、科学を生業としない「一般人」の目で作者が科学を見渡し、本書の内容として選び取った領域を眺めてみるのも興味深い。ぼくは生物学に携わる研究者の端くれだが、本書の後半を占める生命科学で描かれるトピックは、現代生命科学の王道とはかなりズレている。これをビル・ブライソンの偏見とみるか、それとも、生命科学という営みがボタンを掛け違えつつあるのか、考えさせられる。