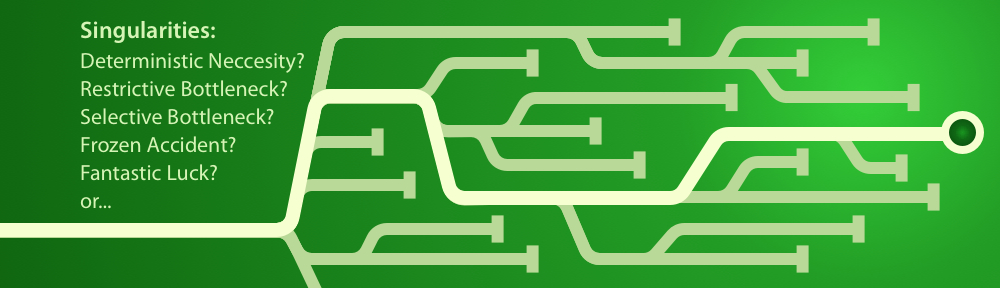横道世之介というどこにでもいそうで、実はなかなか出会えないのかもしれない大学生の東京での最初の1年(おそらくは1987年)を描いた小説。世之介の魅力を数百字で伝えるのは難しい。敢えてまとめれば、彼の魅力はその気負わない前向きさだろう。流れに巻き込まれて、意図せぬ状況に立ち至っても、後悔したり、言い訳したりせずに、とりあえずその状況を生きる。楽しもうとしたり、立ち向かおうとしたりしているようには見えない。そういう気負いはない。受け流しはするが、逃げはしない。後ろ向きではない程度の前向きさ。
横道世之介というどこにでもいそうで、実はなかなか出会えないのかもしれない大学生の東京での最初の1年(おそらくは1987年)を描いた小説。世之介の魅力を数百字で伝えるのは難しい。敢えてまとめれば、彼の魅力はその気負わない前向きさだろう。流れに巻き込まれて、意図せぬ状況に立ち至っても、後悔したり、言い訳したりせずに、とりあえずその状況を生きる。楽しもうとしたり、立ち向かおうとしたりしているようには見えない。そういう気負いはない。受け流しはするが、逃げはしない。後ろ向きではない程度の前向きさ。
作中、まるで過去を回想するように、約20年後の「現在」が挿入される。そこでは、40歳を過ぎて大人になった登場人物たちが、日常の隙間にふと世之介のことを思いだす。そういえばあんなヤツがいたな。おもしろいヤツだったな。あいつと知り合いになれてよかったよな、と。ずっとつきあいがつづいているわけではない。今、どこでどうしているかもわからない。でも、ふとしたきっかけで、楽しい思い出として、ほんの少し思いだす。ぼくはたぶん世之介よりひとつ年下で、やはりいま20年後の「現在」を生きている。ぼくに、そんな人物がどのくらいいるだろうか。
終盤、世之介が恋人のために用意したあるものが、当人の手にわたる。日々、人は人になにかを渡しながら生きる。気楽な思いだったり、重大な意図だったりを込めて。でも、言葉やモノに込めた意味は、そう簡単に正しくは伝わらない。意味は変容し、でも繋がって、受け継がれていく。「横道世之介」の終盤に描かれるのも、そうした弱い連鎖だ。意味を変えながら、手渡されるモノ。その脆さ。でも、表層的な意味が忘れられ、あるいは誤解されても、もっと深いところでは、ちゃんと繋がって、引き継がれていく、その強さ。なんてことのない日常、なんてことのない友人、家族のかけがえのない愛おしさを、そのまんま書いてしまったこと、書けてしまっていることが、この小説を、かけがえなく愛おしいものにしているように思える。
Author Archives: ynaito
数学は最善世界の夢を見るか?
 モーペルテュイの最小作用の原理を中核に据え、人類文明における科学、合理的思考の役割を考察した傑作。原著は、2000年に仏語版が、2006年に仏語版に基づく英語版が上梓されている。英語版では一部内容の削除、追加が行われており、2つの版の印象は異なるようである。そのあたりは「訳者あとがき」に詳しい。
モーペルテュイの最小作用の原理を中核に据え、人類文明における科学、合理的思考の役割を考察した傑作。原著は、2000年に仏語版が、2006年に仏語版に基づく英語版が上梓されている。英語版では一部内容の削除、追加が行われており、2つの版の印象は異なるようである。そのあたりは「訳者あとがき」に詳しい。
翻訳は、より新しい英語版に基づいているが、英語版で削除された仏語版の記述が付録として採録されるなど、いいとこ取りの構成になっている。翻訳者・南條郁子氏の配慮と、みすず書房の良識に感謝、感銘。
著者エクランドがフランス人ということもあるのだろう、本書ではモーペルテュイの他にもデカルト、フェルマー、ラグランジュといったフランスで活躍した研究者への言及が多い。フランス人贔屓というわけではなく、エクランドの教養を形づくっている要素を反映すれば自然なことなのだろう。それが、英米の科学者やサイエンスライタの書くものとは異なったものの見方を生みだしており、おもしろい。
ガリレオの仕事をとっかかりとして、時間とともに変化する運動現象を、どうやって科学の枠組みに捕捉したのかを眺め、代数と幾何という異なる流れの中で発展してきた数学が合流し、運動を理解する上での強力な道具になったことが語られる。
そして、モーペルテュイが、最小作用の原理によって、この世界が最大限効率的に無駄なく作りあげられており、それこそが神の御業の痕跡であると主張する。その周辺で、この世界(宇宙)は、存在可能なあらゆる世界の中で、最善の世界なのかという哲学的な問いに、数学によって挑む試みが繰り返されていく。
やがて科学は神と別れを告げ、テクノロジーと手を結び、さらに発展し、私たちの文明に明暗ともども深く拭い去れない影響を与える。その中で、最小作用の原理は折に触れ再解釈され、そこから最適化理論が派生する。エクランドは、生命科学や経済学といった領域を実例としてあげ、世界が(局所的であれ)最適化されているか、最適化することは可能かを探究する。
科学を最高の武器として駆使し、この世界の成り立ちを理解しようと思索を巡らし、最終的に、合理主義に拠って立つ自らの立場を明解に記述し、こうした思索の積み重ねが、個人的な幸福とどう繋がっていくかにまで言及している。
進化遺伝学
プルーストとイカ
 こんなすばらしい本に、邦訳されて1年以上も気づかずにいたことを反省させられる。そのくらいすばらしいポピュラー・サイエンス。アメリカには、こういう本を書こうとする研究者とそれをサポートする編集者がいて、コンスタントにこういった良い意味で、非専門家のレベルまで「降りてこない」著作が上梓される。
こんなすばらしい本に、邦訳されて1年以上も気づかずにいたことを反省させられる。そのくらいすばらしいポピュラー・サイエンス。アメリカには、こういう本を書こうとする研究者とそれをサポートする編集者がいて、コンスタントにこういった良い意味で、非専門家のレベルまで「降りてこない」著作が上梓される。
タイトルにあるプルーストとイカは、いずれも読字という高度な脳機能のアイコンである。プルーストの文章と読書観は、読字といういうプロセスが機能として現れるマクロ側の一端を象徴し、イカの神経回路は、そのプロセスを支える細胞とそのネットワークというミクロ側の一端を象徴している。このタイトルに象徴されるように、この書物は、読字というプロセスをマクロからミクロまで縦断的に、そして、神経科学から音韻学、言語教育まで横断的に描きだそうとしている。
諸領域で、本当の意味で学際的な研究への取り組みが深化しつつある、この21世紀だからこそ、生まれでた書物といえるかもしれない。
本書は、大きく3つのパートからなる。
パート1は、ヒトという生物が、文字をつくり、文字を読み、文字を他者と共有するという、他の生物種に類を見ない能力をいかにして獲得し、磨きあげてきたかを俯瞰する。生物の身体は、さまざまな機能のために特化した器官を進化を通して獲得している。陸上で呼吸するための肺、歩くための足、飛行するための翼などなど。脳にもさまざまな機能分化があり、見るための領域、運動するための領域などが存在し、独自の神経回路をつくっている。しかし、読むために特化した回路、読むための遺伝子は見つかっていない。読むという能力は、生命進化の時間スケールから見れば、非常に短い期間に獲得されており、読むことに特殊化した装置を進化によって獲得するには至っていないのだ。読むという機能は、ヒトが読むことを始める以前から持っていた脳内の回路を流用することによって実現されている。
パート2は、ひとりのヒトが、成長の過程でどのように読字能力を身につけていくかを描く。見ること、聴くこと、そして話すことは、健常者であれば、教えられなくてもやがてできるようになる。これに対して、読むことは、教えられなければ身につけることのできない能力である。パート1で描かれる読字の歴史でも、もっとも古い文字体系のひとつを開発したシュメール人が、同時に高度な読字教育を行っていたことが示される。パート2では、教育環境が与えられたとき、ヒトの脳がどのように変化し、読むことができる脳へと発達していくのかが概説される。
パート3は、読字に障害のある脳について語られる。著者は、この領域を研究するトップランナーであるとともに、読字障害を抱える息子の母親でもある。パート3冒頭の1節には、著者の熱い想いがこもっている。これ以降を書くために、ここまでの2つのパートがあったのか、とも思える。生物学では、機能の欠失した個体の特性を研究することで、その機能について理解を深めるというアプローチが頻繁にとられ、王道のひとつとなっている。読字を科学的に理解するために、読字障害(ディスレクシア)の研究が重要なのは間違いない。
読字障害の脳の一部では、本来読字において重要な役割を果たす左脳の領域が読字の際に機能せず、それを代償するように右脳が機能し、総合的な処理速度、処理能力において後れをとっていることがわかっている。
従来、それは読字に重要な役割を果たす左脳の神経回路に何らかの機能不全があり、別の領域でそれを代償しようとするがしきれないために読字障害として現れると解釈されてきた。それが、現在では、発達の過程で脳が読字のための回路を構成しようとする時点で、右脳の能力が突出して高いために、本来左脳で構成されるはずの回路を右脳が引き受けてしまうのではないか、という仮説が提案されているという。右脳優位の読字回路は、初歩的な読字には適応するが、後年、求められる読字能力が複雑高度化すると、いかに右脳が優れていても左脳の回路には及ばず、読字障害が発現するというのである。この仮説は、読字障害者に稀有な能力を持つ人物が非常に多いという事実をも説明している。
読むという、できてしまえば日常生活の基本スキルとなってしまっている技術が、いかにすばらしく、また複雑で損なわれやすいものであるかを実感させてくれるすばらしい本。
また作者は、全パートを通じて、物心ついたころからインターネットを利用して情報を得る新たな世代が、読字を巡るたいせつな何かを失うのではないかと、控えめに警鐘を鳴らしている。自分自身もやっていることなので、実感しているが、問題を解決するために、ネットを検索し、材料を寄せ集め、形を整えて一件落着、というやり方は、そのプロセスだけを繰り返していると、情報を右から左に受け流すだけになり、自分の中に形のある何かが残りにくい。作者が危惧するのも、そうした知のあり方が、人類の知の前進にどう影響するかという点だろう。
作中では、古代ギリシャで、文字による知識の記述が始まった頃、当時の大哲人ソクラテスが、文字による知識の記述が人間を衰退させるとして、その流れに真っ向から反対を唱えたことが繰り返し引用される(師の教えに背き、その弟子プラトンがソクラテスの対話を書き残したことによって、私たちはソクラテスの叡智に触れることができるというパラドクスがある)。ソクラテスの嘆きは、一部は正鵠を射ており、一部は的外れだった。そして、膨大なデジタル情報の検索という、新たな情報ハンドリングに移行しつつある現代において、ソクラテスの叱声の意味が甦るのかもしれない、ということだ。
中世の停滞と衰退などに実例を見ることができるように、人類の知は、必ずしも進歩を約束づけられてはいない。自らがつくりだした便利な道具によって、自らの進歩を取りやめてしまう可能性は充分にある。
「標準模型」の宇宙
 素粒子物理学、とりわけ標準模型に関する一般向け解説書。素粒子物理学に関する一般向けの書物は、日本語で読めるものでもかなりの数がある。この分野で日本人ノーベル賞受賞者が出たことでブームにもなった。しかし、ここまで真正面から、手間を惜しまず、標準模型を理解するために必要と思われる要素を一般向けに解説した書物はかつてなかったのではないかと思う。すばらしい。
素粒子物理学、とりわけ標準模型に関する一般向け解説書。素粒子物理学に関する一般向けの書物は、日本語で読めるものでもかなりの数がある。この分野で日本人ノーベル賞受賞者が出たことでブームにもなった。しかし、ここまで真正面から、手間を惜しまず、標準模型を理解するために必要と思われる要素を一般向けに解説した書物はかつてなかったのではないかと思う。すばらしい。
本文だけでも450ページを超える大部だが、密度も相当に高い。前半3分の1で、現代物理学をレビューし、場の量子論まで解説する。中盤の3分の1は、対称性と群論の解説。そして残る3分の1で、それまで解説した「基礎知識」を土台に、ゲージ理論、標準模型など、最新の素粒子物理学の到達点が解説される。
著者自身が「まえがき」で述べているように、この本では、素粒子物理学の歴史や、研究者の人物に関するエピソードには紙数を割いていない。一刻に、素粒子物理学を理解するための解説だけを書いている。これだと、書きようによっては初学者向けの教科書になってしまいそうだ。なのに、読んでいて楽しく、また教科書とは明らかに一線を画していると感じられるのは、著者自身が自分の研究対象を心底楽しんでおり、それを読者に伝えようとしているからだろう。「ほら、面白いでしょう」という著者のワクワクする気持ちが、行間から伝わってくる。
数式を極力排するなど、ポピュラーサイエンスに分類される書物には違いないが、たいていの類書が説明を諦めている部分も正面から説明しようとしており、類書に物足りなさを感じていた読者には喝采ものだろう。
現代自然科学の尖端に真正面から取り組み、成し遂げているのは、すばらしいのひと言に尽きるが、しかしながら、やはり類書に比べれば内容は難しい。例えば、縦書きのポピュラーフィクションで、ファインマンダイアグラムの読み方を丁寧に解説し、実際に数十枚のファインマンダイアグラムを示して現象の解説を試みているような本を、私は他に知らない。
クオーク、対称性、標準模型といった概念について何の知識もない人がいきなり本書に取り組むのは「挑戦」だろう。「ガリレオの指」「もっとも美しい対称性」など、より平易に書かれたポピュラーサイエンスで地ならししてから、本書へと読み進むのがいいように感じる。
素粒子物理学を扱ったポピュラーサイエンスに、本書の次(further reading)は存在しないだろう。この本を読んでさらに知りたいと思ったら、専門書を手にとるしかない。そのくらい高度な内容が、ごまかし抜きに書かれている。(3度目になるが、)すばらしい。
なお、この手の一般向けの書物は、当然ながら著者の考え方が明に暗に現れる。その中には、民族差別的な考えの持ち主であることを想像させるものもある。複数の研究者が同時平行にある発見に至ったような事実に言及するとき、欧米の研究者による成果だけを引き立たせ、日本人をはじめとする他民族の研究者の業績をことさら矮小化して記述する書き手もいて、内容がすばらしければすばらしいほど、残念な思いに駆られる。
本書は、(少なくとも日本人に対しては)非常にフェアである。南部陽一郎、小柴昌俊、益川敏英、小林誠らの業績が深い経緯とともに紹介されている。特に、南部陽一郎に対しては尊敬の念を抱いていることが伺われるが、これは、そもそも南部の業績が先駆的で偉大なものであることに加え、筆者がシカゴ大学で博士号を取得していることに関係しているかもしれない。筆者は実験物理学者、南部は理論物理学者なので、師弟関係ということはないだろうが、筆者の在籍当時、南部はシカゴ大学で教鞭を執っており、講義を聴いたことは十分に考えられる。
化学系・生物系の計算モデル
 共立出版のアルゴリズム・サイエンスシリーズの適用事例編の一冊。アルゴリズムの観点から、化学、生物学における数理モデルを俯瞰している。数理モデルの中でも、計算可能なモデルという意味で「計算モデル」という呼び名を使っている。
共立出版のアルゴリズム・サイエンスシリーズの適用事例編の一冊。アルゴリズムの観点から、化学、生物学における数理モデルを俯瞰している。数理モデルの中でも、計算可能なモデルという意味で「計算モデル」という呼び名を使っている。
数理モデル化の手法と、モデルを計算する手法の両方を一冊の書籍の中で幅広く概説するテキストは、日本語で読めるものとしてはほとんど例がないのではないかと思われる。
構成としては、第1章で、化学系、生物系の特徴と、それらの対象をモデル化する際に考慮すべき点を概観し、それらを状態遷移系として捉えることができるとする視点が示される。第2章は、状態遷移系に関する概論。
第3章は、数理モデルを計算するアルゴリズムの概説で、微分方程式による決定論シミュレーションとGillespieアルゴリズムによる確率論シミュレーションが説明されている。コンパクトであるが、Gillespieアルゴリズムに関連する τ-leaping 法に1節を割くなど、実践的な内容になっている。
第4章は「膜構造を持つ計算モデル」と題して、並列計算モデルの π calculus などを概説している。細胞内の化学反応は、いうまでもなく超並列に進行している。
第5章は、空間を含む場におけるモデリングの概説で、セル・オートマトン、ブーリアンネットワーク、ニューラル・ネットワーク、有限要素法など、多彩な話題に触れている。
第6章では、離散アルゴリズムと連続アルゴリズムを融合して計算する例として、ハイブリッド・オートマトンと、ハイブリッド・ペトリネットを紹介している。
200ページ足らずの中にこれだけの内容を詰め込んでいるため、個々の話題への踏み込み方は決して深くないが、そのあたりは、アルゴリズム・サイエンスシリーズの他の巻に当たるなどすべし、ということだろう。
繰り返しになるが、こうした視点で編まれた化学・生物学シミュレーションのテキストは稀であり、得られる知識を勘案するとコストパフォーマンスの高い一冊だと思う。
生命の音楽—ゲノムを超えて
 心臓の電気生理学の第一人者Denis Nobleによる一般向けのシステム生物学の本。原著は2006年。Noble博士とは、7〜8年前に一度だけ夕食をともにする機会があった。日本人研究者につけてもらった漢字の名前を持っていると仰り、箸袋に「貴」の字をご自分で書いていたのが記憶に残っている(Noble→貴なのだろう。漢字名そのものは失念)。本書でも、日本をはじめ、東洋哲学を数多く引き合いに出すなど、東洋に親しい側面が度々顕れている。
心臓の電気生理学の第一人者Denis Nobleによる一般向けのシステム生物学の本。原著は2006年。Noble博士とは、7〜8年前に一度だけ夕食をともにする機会があった。日本人研究者につけてもらった漢字の名前を持っていると仰り、箸袋に「貴」の字をご自分で書いていたのが記憶に残っている(Noble→貴なのだろう。漢字名そのものは失念)。本書でも、日本をはじめ、東洋哲学を数多く引き合いに出すなど、東洋に親しい側面が度々顕れている。
「生命の音楽」は生理学のトップランナーが著したシステム生物学の本である。そもそも、生理学は機能に注目して生命現象の理解に取り組む学問領域であり、古くからこれと競い合う分野に生化学などがある。学部生だった頃、免疫学の教授が披露した「生理学者は”最初に磨りつぶしてしまって、生き物の何がわかるのか”と、生化学者を詰り、生化学者は”生き物のように複雑なものを、そのまま観察して何を理解できるのか”と反撃する」というジョークが今も脳裡に鮮やかに残っている。
生命の機能という複雑な現象を記述し、解明するために、生理学では数学を用いたモデル化が活用されてきた。しかし、20世紀半ば以降の分子生物学の絶対的な繁栄により、分子レベルの生物学が圧倒的な勢いを得ると、その大局に位置する生理学は失速していった。10年ほど前、日本を代表する電気生理学者が「日本の大学には”生理学”と名のつく研究室がほとんどなくなってしまった」とこぼされていた。
システム生物学は、世紀の変わり目を跨ぐころに、分子細胞生物学をはじめとする膨大な生命科学の知識を統合し、生命現象を理解するアプローチとして、北野宏明らによって提唱されたもので、現在では、若干その意味を変えながら生命科学の領域に定着しつつある。定着する過程で、システム生物学の提唱するアプローチは真新しいものではない、という批判がそこかしこで聴かれた。生理学者たちも大いに憤慨したひとりではないかと思う。確かに、生理学は機能というマクロな階層に軸足を置くアプローチであり、また、現代の生理学は分子レベルの知見や技術を活用し、機能から分子へ、マクロからミクロへと階層を横断する研究領域へと発展しており、システム生物学の趣旨と重なる部分はかなり大きい。
「生命の音楽」は生理学者Nobleならではの本になっている。解明したい対象は、生命現象である、という視点が、終始一貫、ブレることなく中心にある。これは爽快だ。生命科学の主たる目的が、生命現象の解明にある、なんてことは自明のようだが、現実の生命科学の営みは決してそうはなっていない。分子レベルのアプローチがあまりにも突出して進歩してしまったため、分子レベルのアプローチが目的としていること、あるいは解明の対象としていることが、あたかも生命科学全体の目的であるかのように物語られる局面に出くわすことが少なくない。
「生命の音楽」では、音楽をキーとなる比喩に据え、生命現象を解明し、理解するために、どういった視座を持つべきかが論じられる。ゲノムは「楽譜」なのか、生命システムに「指揮者」はいるのか、という具合に。10の章には、それぞれ、音楽に関わる題名が与えられている。比喩を縦横に駆使しながら、その力と背中合わせに存在する危険性についても慎重に論じており、興味深い。
全編を通して主張されているのは、分子、細胞、個体といった階層のどれかに限局してしまっては生命現象を理解することは難しく、複数の階層を往還しつつ、対象となる生命現象にとって適切な視座を持たなければならない、ということだ。ゲノムは単なる情報であり、ゲノム情報を転写翻訳する細胞システムがあって初めて、この物理世界における意味や機能が発生するという記述に、昨年亡くなった物理学者John Wheelerが「床に書かれた方程式に、どんなに命令しても方程式が飛ぶことはない」と話していたことを思いだした。
翻訳は我が国の心臓の電気生理学の第一人者である倉智嘉久教授が手がけている。研究者が翻訳した書物は読みにくいことが少なくないが、本書の翻訳はすばらしい。科学的な内容に不安がないのはもちろん、日本語としても自然で読みやすいものになっている。あとがきに、Noble博士自身から倉智教授に依頼があったとあるが、最善の選択だったのではないかと感じる。
生命とは何か それからの50年
 1943年、シュレーディンガーがナチスの手を逃れて亡命したアイルランド・ダブリンのトリニティカレッジで、専門分野とは異なる生命に関する講義を行った。その講義録「生命とは何か」は物理学者をはじめとする多くの科学者を生命科学の領域へと誘い、二重らせんDNAの発見のきっかけになったとされている。
1943年、シュレーディンガーがナチスの手を逃れて亡命したアイルランド・ダブリンのトリニティカレッジで、専門分野とは異なる生命に関する講義を行った。その講義録「生命とは何か」は物理学者をはじめとする多くの科学者を生命科学の領域へと誘い、二重らせんDNAの発見のきっかけになったとされている。
その記念すべき講義から50年にあたる1993年、同じダブリン・トリニティカレッジに「生命とは何か」を追及する当代超一流の研究者たちが招聘され、シュレーディンガーへの50年後の回答をそれぞれ講演した。本書はその講演録である。
演者の顔ぶれは凄いという言葉では語り尽くせない破格ぶり。グールド、ペンローズ、カウフマン、ジャレド・ダイアモンド、メイナード=スミス、ド・デュープ、ウォルパート、アイゲン、ティリング、ハーケン……1冊の書物で、これだけの顔ぶれの研究者というか賢者たちの当時最先端の考えを読めるものは絶無といっても過言ではないだろう。
すでにこの講演会からも15年以上の月日が流れ、グールド、メイナード=スミスといった講演者の一部も鬼籍に入った。しかし「生命とは何か」という生命科学でもっとも簡潔かつ最大の問いに正面から答えようとしたそれぞれの講演は、総じて、年月を経てもその鋭さは衰えておらず、今読んでも大いに刺激的。
最終章は講演会のバンケットにおいてシュレーディンガーの息女ルース・ブラウニツァーが講演した父の回想で、これもまた、貴重な掌編。
それぞれの講演は、多岐、複雑、高度な内容で、必ずしもわかりやすい内容とはいえないが、多彩な立場の研究者が、きっぱりと自分の生命観を述べており、読む者を刺激するアイディアや思索が高密度に詰まっている。
きのうの世界
 恩田陸の超絶的な「かたり」の技巧が炸裂している作品です。ミステリー、ホラー、ファンタジーといったあらゆるジャンルの要素を鏤めつつ、あらゆるジャンル小説として中途半端です。でも、この作品は、そもそもどんなジャンル小説でもないように感じました。読み方はいろいろあるし、結果としてこの作品を気に入る人もそうでない人もいると思いますが、ぼくは星5つつけます。ぼくはこの小説を視点に関する技巧を凝らし、物語世界を俯瞰する視点とは何なのかについて思いを凝らした物語として読みました。というか、読み終えてそう感じ入りました。目次を見ても、この小説にとって視点が重要であることが明示されていると思います。
恩田陸の超絶的な「かたり」の技巧が炸裂している作品です。ミステリー、ホラー、ファンタジーといったあらゆるジャンルの要素を鏤めつつ、あらゆるジャンル小説として中途半端です。でも、この作品は、そもそもどんなジャンル小説でもないように感じました。読み方はいろいろあるし、結果としてこの作品を気に入る人もそうでない人もいると思いますが、ぼくは星5つつけます。ぼくはこの小説を視点に関する技巧を凝らし、物語世界を俯瞰する視点とは何なのかについて思いを凝らした物語として読みました。というか、読み終えてそう感じ入りました。目次を見ても、この小説にとって視点が重要であることが明示されていると思います。
この小説の冒頭は二人称という珍しい視点ではじまります。しかも、中心となる「あなた」が知り得ないこともどんどん語られ、二人称としての整合性が簡単に破られていきます。違和感のある描写の行間に登場人物を「あなた」と呼ぶ「語り手」の存在が暗示されているようにぼくは感じました。
19章と3つの「幕間」からなる物語は、変幻自在に視点を変えていきます。物語としてのクライマックス、今日と昨日を隔絶するある大掛かりな出来事が描かれたあと、短い2章を添えて、物語は締めくくられます。この2章では、主にある一人の人物について語られますが、それぞれの章で視点が切り替わります。そして、最後の1ページで、さらに語りの視点が異様なものに変容します。最後の1ページに現れたこの視点こそが、冒頭である人物を「あなた」と呼んだ語り手の視点なのだろうと、ぼくは解釈しました。そうした異形の視点の存在そのものが、この物語を象徴しています。「これ」を「このように」書こうとする着想が凄まじいし、すばらしいと思います。
遺伝子には何ができないか
 分子細胞生物学をコアとする現代の生命科学が孕んでいる誤謬と、それに起因して突き当たるかもしれない限界について主張する論考。筆者は生化学と哲学のダブルドクター。
分子細胞生物学をコアとする現代の生命科学が孕んでいる誤謬と、それに起因して突き当たるかもしれない限界について主張する論考。筆者は生化学と哲学のダブルドクター。
現代の生命科学における遺伝子が、巨視的な表現型を反映する遺伝子Pと、分子レベルのDNA配列を指す遺伝子Dというまったく別の2つの概念の「つぎはぎ」であり、両者がシームレスに連結可能であるという根拠のない前提がそこに潜んでいる危険性を指摘する。そして、この概念が成立する過程を振り返り、シュレーディンガーによる記念碑的講義と、ワトソンとクリックによるその予言への解答が「つぎはぎ遺伝子」概念を強固なものにしたと主張する。
「生命システムのすべては遺伝子(ゲノム)にコードされている」という言明に疑問を感じない人にこそ、一読の価値のある示唆に富んだ優れた一冊。