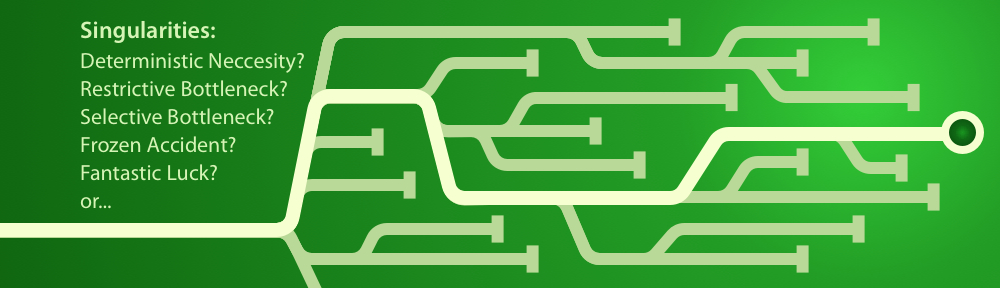恩田陸の超絶的な「かたり」の技巧が炸裂している作品です。ミステリー、ホラー、ファンタジーといったあらゆるジャンルの要素を鏤めつつ、あらゆるジャンル小説として中途半端です。でも、この作品は、そもそもどんなジャンル小説でもないように感じました。読み方はいろいろあるし、結果としてこの作品を気に入る人もそうでない人もいると思いますが、ぼくは星5つつけます。ぼくはこの小説を視点に関する技巧を凝らし、物語世界を俯瞰する視点とは何なのかについて思いを凝らした物語として読みました。というか、読み終えてそう感じ入りました。目次を見ても、この小説にとって視点が重要であることが明示されていると思います。
恩田陸の超絶的な「かたり」の技巧が炸裂している作品です。ミステリー、ホラー、ファンタジーといったあらゆるジャンルの要素を鏤めつつ、あらゆるジャンル小説として中途半端です。でも、この作品は、そもそもどんなジャンル小説でもないように感じました。読み方はいろいろあるし、結果としてこの作品を気に入る人もそうでない人もいると思いますが、ぼくは星5つつけます。ぼくはこの小説を視点に関する技巧を凝らし、物語世界を俯瞰する視点とは何なのかについて思いを凝らした物語として読みました。というか、読み終えてそう感じ入りました。目次を見ても、この小説にとって視点が重要であることが明示されていると思います。
この小説の冒頭は二人称という珍しい視点ではじまります。しかも、中心となる「あなた」が知り得ないこともどんどん語られ、二人称としての整合性が簡単に破られていきます。違和感のある描写の行間に登場人物を「あなた」と呼ぶ「語り手」の存在が暗示されているようにぼくは感じました。
19章と3つの「幕間」からなる物語は、変幻自在に視点を変えていきます。物語としてのクライマックス、今日と昨日を隔絶するある大掛かりな出来事が描かれたあと、短い2章を添えて、物語は締めくくられます。この2章では、主にある一人の人物について語られますが、それぞれの章で視点が切り替わります。そして、最後の1ページで、さらに語りの視点が異様なものに変容します。最後の1ページに現れたこの視点こそが、冒頭である人物を「あなた」と呼んだ語り手の視点なのだろうと、ぼくは解釈しました。そうした異形の視点の存在そのものが、この物語を象徴しています。「これ」を「このように」書こうとする着想が凄まじいし、すばらしいと思います。
Naito Lab
Computer Simulation of Evolutionary Transitions