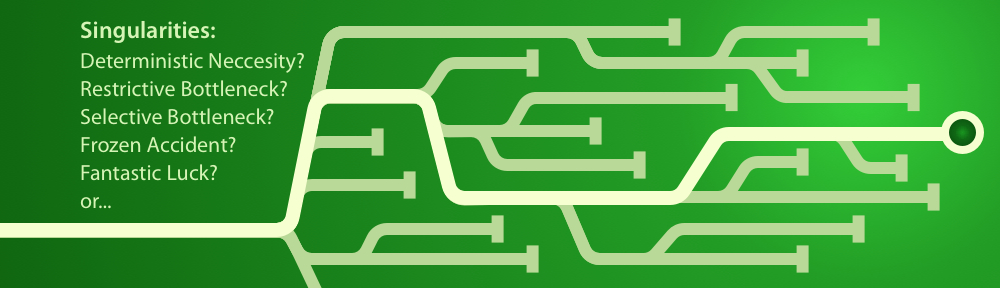横道世之介というどこにでもいそうで、実はなかなか出会えないのかもしれない大学生の東京での最初の1年(おそらくは1987年)を描いた小説。世之介の魅力を数百字で伝えるのは難しい。敢えてまとめれば、彼の魅力はその気負わない前向きさだろう。流れに巻き込まれて、意図せぬ状況に立ち至っても、後悔したり、言い訳したりせずに、とりあえずその状況を生きる。楽しもうとしたり、立ち向かおうとしたりしているようには見えない。そういう気負いはない。受け流しはするが、逃げはしない。後ろ向きではない程度の前向きさ。
横道世之介というどこにでもいそうで、実はなかなか出会えないのかもしれない大学生の東京での最初の1年(おそらくは1987年)を描いた小説。世之介の魅力を数百字で伝えるのは難しい。敢えてまとめれば、彼の魅力はその気負わない前向きさだろう。流れに巻き込まれて、意図せぬ状況に立ち至っても、後悔したり、言い訳したりせずに、とりあえずその状況を生きる。楽しもうとしたり、立ち向かおうとしたりしているようには見えない。そういう気負いはない。受け流しはするが、逃げはしない。後ろ向きではない程度の前向きさ。
作中、まるで過去を回想するように、約20年後の「現在」が挿入される。そこでは、40歳を過ぎて大人になった登場人物たちが、日常の隙間にふと世之介のことを思いだす。そういえばあんなヤツがいたな。おもしろいヤツだったな。あいつと知り合いになれてよかったよな、と。ずっとつきあいがつづいているわけではない。今、どこでどうしているかもわからない。でも、ふとしたきっかけで、楽しい思い出として、ほんの少し思いだす。ぼくはたぶん世之介よりひとつ年下で、やはりいま20年後の「現在」を生きている。ぼくに、そんな人物がどのくらいいるだろうか。
終盤、世之介が恋人のために用意したあるものが、当人の手にわたる。日々、人は人になにかを渡しながら生きる。気楽な思いだったり、重大な意図だったりを込めて。でも、言葉やモノに込めた意味は、そう簡単に正しくは伝わらない。意味は変容し、でも繋がって、受け継がれていく。「横道世之介」の終盤に描かれるのも、そうした弱い連鎖だ。意味を変えながら、手渡されるモノ。その脆さ。でも、表層的な意味が忘れられ、あるいは誤解されても、もっと深いところでは、ちゃんと繋がって、引き継がれていく、その強さ。なんてことのない日常、なんてことのない友人、家族のかけがえのない愛おしさを、そのまんま書いてしまったこと、書けてしまっていることが、この小説を、かけがえなく愛おしいものにしているように思える。
Naito Lab
Computer Simulation of Evolutionary Transitions