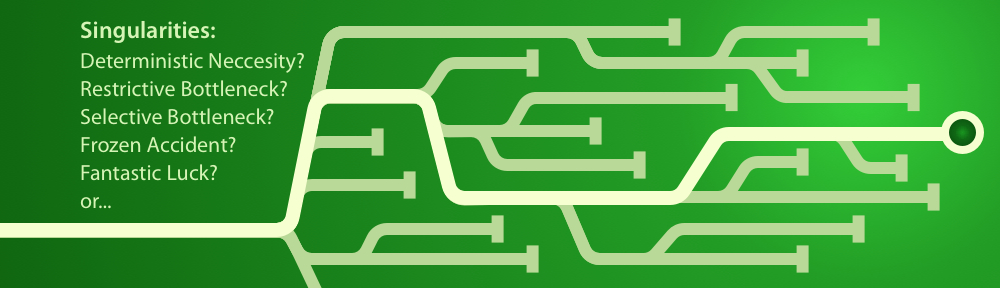こんなすばらしい本に、邦訳されて1年以上も気づかずにいたことを反省させられる。そのくらいすばらしいポピュラー・サイエンス。アメリカには、こういう本を書こうとする研究者とそれをサポートする編集者がいて、コンスタントにこういった良い意味で、非専門家のレベルまで「降りてこない」著作が上梓される。
こんなすばらしい本に、邦訳されて1年以上も気づかずにいたことを反省させられる。そのくらいすばらしいポピュラー・サイエンス。アメリカには、こういう本を書こうとする研究者とそれをサポートする編集者がいて、コンスタントにこういった良い意味で、非専門家のレベルまで「降りてこない」著作が上梓される。
タイトルにあるプルーストとイカは、いずれも読字という高度な脳機能のアイコンである。プルーストの文章と読書観は、読字といういうプロセスが機能として現れるマクロ側の一端を象徴し、イカの神経回路は、そのプロセスを支える細胞とそのネットワークというミクロ側の一端を象徴している。このタイトルに象徴されるように、この書物は、読字というプロセスをマクロからミクロまで縦断的に、そして、神経科学から音韻学、言語教育まで横断的に描きだそうとしている。
諸領域で、本当の意味で学際的な研究への取り組みが深化しつつある、この21世紀だからこそ、生まれでた書物といえるかもしれない。
本書は、大きく3つのパートからなる。
パート1は、ヒトという生物が、文字をつくり、文字を読み、文字を他者と共有するという、他の生物種に類を見ない能力をいかにして獲得し、磨きあげてきたかを俯瞰する。生物の身体は、さまざまな機能のために特化した器官を進化を通して獲得している。陸上で呼吸するための肺、歩くための足、飛行するための翼などなど。脳にもさまざまな機能分化があり、見るための領域、運動するための領域などが存在し、独自の神経回路をつくっている。しかし、読むために特化した回路、読むための遺伝子は見つかっていない。読むという能力は、生命進化の時間スケールから見れば、非常に短い期間に獲得されており、読むことに特殊化した装置を進化によって獲得するには至っていないのだ。読むという機能は、ヒトが読むことを始める以前から持っていた脳内の回路を流用することによって実現されている。
パート2は、ひとりのヒトが、成長の過程でどのように読字能力を身につけていくかを描く。見ること、聴くこと、そして話すことは、健常者であれば、教えられなくてもやがてできるようになる。これに対して、読むことは、教えられなければ身につけることのできない能力である。パート1で描かれる読字の歴史でも、もっとも古い文字体系のひとつを開発したシュメール人が、同時に高度な読字教育を行っていたことが示される。パート2では、教育環境が与えられたとき、ヒトの脳がどのように変化し、読むことができる脳へと発達していくのかが概説される。
パート3は、読字に障害のある脳について語られる。著者は、この領域を研究するトップランナーであるとともに、読字障害を抱える息子の母親でもある。パート3冒頭の1節には、著者の熱い想いがこもっている。これ以降を書くために、ここまでの2つのパートがあったのか、とも思える。生物学では、機能の欠失した個体の特性を研究することで、その機能について理解を深めるというアプローチが頻繁にとられ、王道のひとつとなっている。読字を科学的に理解するために、読字障害(ディスレクシア)の研究が重要なのは間違いない。
読字障害の脳の一部では、本来読字において重要な役割を果たす左脳の領域が読字の際に機能せず、それを代償するように右脳が機能し、総合的な処理速度、処理能力において後れをとっていることがわかっている。
従来、それは読字に重要な役割を果たす左脳の神経回路に何らかの機能不全があり、別の領域でそれを代償しようとするがしきれないために読字障害として現れると解釈されてきた。それが、現在では、発達の過程で脳が読字のための回路を構成しようとする時点で、右脳の能力が突出して高いために、本来左脳で構成されるはずの回路を右脳が引き受けてしまうのではないか、という仮説が提案されているという。右脳優位の読字回路は、初歩的な読字には適応するが、後年、求められる読字能力が複雑高度化すると、いかに右脳が優れていても左脳の回路には及ばず、読字障害が発現するというのである。この仮説は、読字障害者に稀有な能力を持つ人物が非常に多いという事実をも説明している。
読むという、できてしまえば日常生活の基本スキルとなってしまっている技術が、いかにすばらしく、また複雑で損なわれやすいものであるかを実感させてくれるすばらしい本。
また作者は、全パートを通じて、物心ついたころからインターネットを利用して情報を得る新たな世代が、読字を巡るたいせつな何かを失うのではないかと、控えめに警鐘を鳴らしている。自分自身もやっていることなので、実感しているが、問題を解決するために、ネットを検索し、材料を寄せ集め、形を整えて一件落着、というやり方は、そのプロセスだけを繰り返していると、情報を右から左に受け流すだけになり、自分の中に形のある何かが残りにくい。作者が危惧するのも、そうした知のあり方が、人類の知の前進にどう影響するかという点だろう。
作中では、古代ギリシャで、文字による知識の記述が始まった頃、当時の大哲人ソクラテスが、文字による知識の記述が人間を衰退させるとして、その流れに真っ向から反対を唱えたことが繰り返し引用される(師の教えに背き、その弟子プラトンがソクラテスの対話を書き残したことによって、私たちはソクラテスの叡智に触れることができるというパラドクスがある)。ソクラテスの嘆きは、一部は正鵠を射ており、一部は的外れだった。そして、膨大なデジタル情報の検索という、新たな情報ハンドリングに移行しつつある現代において、ソクラテスの叱声の意味が甦るのかもしれない、ということだ。
中世の停滞と衰退などに実例を見ることができるように、人類の知は、必ずしも進歩を約束づけられてはいない。自らがつくりだした便利な道具によって、自らの進歩を取りやめてしまう可能性は充分にある。
Naito Lab
Computer Simulation of Evolutionary Transitions