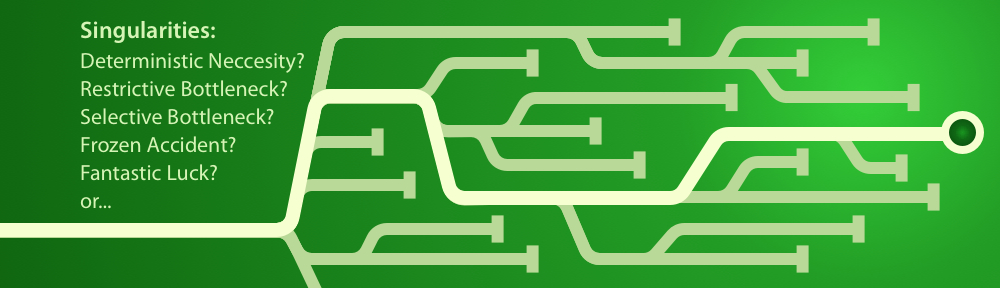共立出版のアルゴリズム・サイエンスシリーズの適用事例編の一冊。アルゴリズムの観点から、化学、生物学における数理モデルを俯瞰している。数理モデルの中でも、計算可能なモデルという意味で「計算モデル」という呼び名を使っている。
共立出版のアルゴリズム・サイエンスシリーズの適用事例編の一冊。アルゴリズムの観点から、化学、生物学における数理モデルを俯瞰している。数理モデルの中でも、計算可能なモデルという意味で「計算モデル」という呼び名を使っている。
数理モデル化の手法と、モデルを計算する手法の両方を一冊の書籍の中で幅広く概説するテキストは、日本語で読めるものとしてはほとんど例がないのではないかと思われる。
構成としては、第1章で、化学系、生物系の特徴と、それらの対象をモデル化する際に考慮すべき点を概観し、それらを状態遷移系として捉えることができるとする視点が示される。第2章は、状態遷移系に関する概論。
第3章は、数理モデルを計算するアルゴリズムの概説で、微分方程式による決定論シミュレーションとGillespieアルゴリズムによる確率論シミュレーションが説明されている。コンパクトであるが、Gillespieアルゴリズムに関連する τ-leaping 法に1節を割くなど、実践的な内容になっている。
第4章は「膜構造を持つ計算モデル」と題して、並列計算モデルの π calculus などを概説している。細胞内の化学反応は、いうまでもなく超並列に進行している。
第5章は、空間を含む場におけるモデリングの概説で、セル・オートマトン、ブーリアンネットワーク、ニューラル・ネットワーク、有限要素法など、多彩な話題に触れている。
第6章では、離散アルゴリズムと連続アルゴリズムを融合して計算する例として、ハイブリッド・オートマトンと、ハイブリッド・ペトリネットを紹介している。
200ページ足らずの中にこれだけの内容を詰め込んでいるため、個々の話題への踏み込み方は決して深くないが、そのあたりは、アルゴリズム・サイエンスシリーズの他の巻に当たるなどすべし、ということだろう。
繰り返しになるが、こうした視点で編まれた化学・生物学シミュレーションのテキストは稀であり、得られる知識を勘案するとコストパフォーマンスの高い一冊だと思う。
Category Archives: Book Review
生命の音楽—ゲノムを超えて
 心臓の電気生理学の第一人者Denis Nobleによる一般向けのシステム生物学の本。原著は2006年。Noble博士とは、7〜8年前に一度だけ夕食をともにする機会があった。日本人研究者につけてもらった漢字の名前を持っていると仰り、箸袋に「貴」の字をご自分で書いていたのが記憶に残っている(Noble→貴なのだろう。漢字名そのものは失念)。本書でも、日本をはじめ、東洋哲学を数多く引き合いに出すなど、東洋に親しい側面が度々顕れている。
心臓の電気生理学の第一人者Denis Nobleによる一般向けのシステム生物学の本。原著は2006年。Noble博士とは、7〜8年前に一度だけ夕食をともにする機会があった。日本人研究者につけてもらった漢字の名前を持っていると仰り、箸袋に「貴」の字をご自分で書いていたのが記憶に残っている(Noble→貴なのだろう。漢字名そのものは失念)。本書でも、日本をはじめ、東洋哲学を数多く引き合いに出すなど、東洋に親しい側面が度々顕れている。
「生命の音楽」は生理学のトップランナーが著したシステム生物学の本である。そもそも、生理学は機能に注目して生命現象の理解に取り組む学問領域であり、古くからこれと競い合う分野に生化学などがある。学部生だった頃、免疫学の教授が披露した「生理学者は”最初に磨りつぶしてしまって、生き物の何がわかるのか”と、生化学者を詰り、生化学者は”生き物のように複雑なものを、そのまま観察して何を理解できるのか”と反撃する」というジョークが今も脳裡に鮮やかに残っている。
生命の機能という複雑な現象を記述し、解明するために、生理学では数学を用いたモデル化が活用されてきた。しかし、20世紀半ば以降の分子生物学の絶対的な繁栄により、分子レベルの生物学が圧倒的な勢いを得ると、その大局に位置する生理学は失速していった。10年ほど前、日本を代表する電気生理学者が「日本の大学には”生理学”と名のつく研究室がほとんどなくなってしまった」とこぼされていた。
システム生物学は、世紀の変わり目を跨ぐころに、分子細胞生物学をはじめとする膨大な生命科学の知識を統合し、生命現象を理解するアプローチとして、北野宏明らによって提唱されたもので、現在では、若干その意味を変えながら生命科学の領域に定着しつつある。定着する過程で、システム生物学の提唱するアプローチは真新しいものではない、という批判がそこかしこで聴かれた。生理学者たちも大いに憤慨したひとりではないかと思う。確かに、生理学は機能というマクロな階層に軸足を置くアプローチであり、また、現代の生理学は分子レベルの知見や技術を活用し、機能から分子へ、マクロからミクロへと階層を横断する研究領域へと発展しており、システム生物学の趣旨と重なる部分はかなり大きい。
「生命の音楽」は生理学者Nobleならではの本になっている。解明したい対象は、生命現象である、という視点が、終始一貫、ブレることなく中心にある。これは爽快だ。生命科学の主たる目的が、生命現象の解明にある、なんてことは自明のようだが、現実の生命科学の営みは決してそうはなっていない。分子レベルのアプローチがあまりにも突出して進歩してしまったため、分子レベルのアプローチが目的としていること、あるいは解明の対象としていることが、あたかも生命科学全体の目的であるかのように物語られる局面に出くわすことが少なくない。
「生命の音楽」では、音楽をキーとなる比喩に据え、生命現象を解明し、理解するために、どういった視座を持つべきかが論じられる。ゲノムは「楽譜」なのか、生命システムに「指揮者」はいるのか、という具合に。10の章には、それぞれ、音楽に関わる題名が与えられている。比喩を縦横に駆使しながら、その力と背中合わせに存在する危険性についても慎重に論じており、興味深い。
全編を通して主張されているのは、分子、細胞、個体といった階層のどれかに限局してしまっては生命現象を理解することは難しく、複数の階層を往還しつつ、対象となる生命現象にとって適切な視座を持たなければならない、ということだ。ゲノムは単なる情報であり、ゲノム情報を転写翻訳する細胞システムがあって初めて、この物理世界における意味や機能が発生するという記述に、昨年亡くなった物理学者John Wheelerが「床に書かれた方程式に、どんなに命令しても方程式が飛ぶことはない」と話していたことを思いだした。
翻訳は我が国の心臓の電気生理学の第一人者である倉智嘉久教授が手がけている。研究者が翻訳した書物は読みにくいことが少なくないが、本書の翻訳はすばらしい。科学的な内容に不安がないのはもちろん、日本語としても自然で読みやすいものになっている。あとがきに、Noble博士自身から倉智教授に依頼があったとあるが、最善の選択だったのではないかと感じる。
生命とは何か それからの50年
 1943年、シュレーディンガーがナチスの手を逃れて亡命したアイルランド・ダブリンのトリニティカレッジで、専門分野とは異なる生命に関する講義を行った。その講義録「生命とは何か」は物理学者をはじめとする多くの科学者を生命科学の領域へと誘い、二重らせんDNAの発見のきっかけになったとされている。
1943年、シュレーディンガーがナチスの手を逃れて亡命したアイルランド・ダブリンのトリニティカレッジで、専門分野とは異なる生命に関する講義を行った。その講義録「生命とは何か」は物理学者をはじめとする多くの科学者を生命科学の領域へと誘い、二重らせんDNAの発見のきっかけになったとされている。
その記念すべき講義から50年にあたる1993年、同じダブリン・トリニティカレッジに「生命とは何か」を追及する当代超一流の研究者たちが招聘され、シュレーディンガーへの50年後の回答をそれぞれ講演した。本書はその講演録である。
演者の顔ぶれは凄いという言葉では語り尽くせない破格ぶり。グールド、ペンローズ、カウフマン、ジャレド・ダイアモンド、メイナード=スミス、ド・デュープ、ウォルパート、アイゲン、ティリング、ハーケン……1冊の書物で、これだけの顔ぶれの研究者というか賢者たちの当時最先端の考えを読めるものは絶無といっても過言ではないだろう。
すでにこの講演会からも15年以上の月日が流れ、グールド、メイナード=スミスといった講演者の一部も鬼籍に入った。しかし「生命とは何か」という生命科学でもっとも簡潔かつ最大の問いに正面から答えようとしたそれぞれの講演は、総じて、年月を経てもその鋭さは衰えておらず、今読んでも大いに刺激的。
最終章は講演会のバンケットにおいてシュレーディンガーの息女ルース・ブラウニツァーが講演した父の回想で、これもまた、貴重な掌編。
それぞれの講演は、多岐、複雑、高度な内容で、必ずしもわかりやすい内容とはいえないが、多彩な立場の研究者が、きっぱりと自分の生命観を述べており、読む者を刺激するアイディアや思索が高密度に詰まっている。
きのうの世界
 恩田陸の超絶的な「かたり」の技巧が炸裂している作品です。ミステリー、ホラー、ファンタジーといったあらゆるジャンルの要素を鏤めつつ、あらゆるジャンル小説として中途半端です。でも、この作品は、そもそもどんなジャンル小説でもないように感じました。読み方はいろいろあるし、結果としてこの作品を気に入る人もそうでない人もいると思いますが、ぼくは星5つつけます。ぼくはこの小説を視点に関する技巧を凝らし、物語世界を俯瞰する視点とは何なのかについて思いを凝らした物語として読みました。というか、読み終えてそう感じ入りました。目次を見ても、この小説にとって視点が重要であることが明示されていると思います。
恩田陸の超絶的な「かたり」の技巧が炸裂している作品です。ミステリー、ホラー、ファンタジーといったあらゆるジャンルの要素を鏤めつつ、あらゆるジャンル小説として中途半端です。でも、この作品は、そもそもどんなジャンル小説でもないように感じました。読み方はいろいろあるし、結果としてこの作品を気に入る人もそうでない人もいると思いますが、ぼくは星5つつけます。ぼくはこの小説を視点に関する技巧を凝らし、物語世界を俯瞰する視点とは何なのかについて思いを凝らした物語として読みました。というか、読み終えてそう感じ入りました。目次を見ても、この小説にとって視点が重要であることが明示されていると思います。
この小説の冒頭は二人称という珍しい視点ではじまります。しかも、中心となる「あなた」が知り得ないこともどんどん語られ、二人称としての整合性が簡単に破られていきます。違和感のある描写の行間に登場人物を「あなた」と呼ぶ「語り手」の存在が暗示されているようにぼくは感じました。
19章と3つの「幕間」からなる物語は、変幻自在に視点を変えていきます。物語としてのクライマックス、今日と昨日を隔絶するある大掛かりな出来事が描かれたあと、短い2章を添えて、物語は締めくくられます。この2章では、主にある一人の人物について語られますが、それぞれの章で視点が切り替わります。そして、最後の1ページで、さらに語りの視点が異様なものに変容します。最後の1ページに現れたこの視点こそが、冒頭である人物を「あなた」と呼んだ語り手の視点なのだろうと、ぼくは解釈しました。そうした異形の視点の存在そのものが、この物語を象徴しています。「これ」を「このように」書こうとする着想が凄まじいし、すばらしいと思います。
遺伝子には何ができないか
 分子細胞生物学をコアとする現代の生命科学が孕んでいる誤謬と、それに起因して突き当たるかもしれない限界について主張する論考。筆者は生化学と哲学のダブルドクター。
分子細胞生物学をコアとする現代の生命科学が孕んでいる誤謬と、それに起因して突き当たるかもしれない限界について主張する論考。筆者は生化学と哲学のダブルドクター。
現代の生命科学における遺伝子が、巨視的な表現型を反映する遺伝子Pと、分子レベルのDNA配列を指す遺伝子Dというまったく別の2つの概念の「つぎはぎ」であり、両者がシームレスに連結可能であるという根拠のない前提がそこに潜んでいる危険性を指摘する。そして、この概念が成立する過程を振り返り、シュレーディンガーによる記念碑的講義と、ワトソンとクリックによるその予言への解答が「つぎはぎ遺伝子」概念を強固なものにしたと主張する。
「生命システムのすべては遺伝子(ゲノム)にコードされている」という言明に疑問を感じない人にこそ、一読の価値のある示唆に富んだ優れた一冊。
告白
 年末に購入していたが、やっと読めた。読みはじめたら一気だった。そのくらい、読ませるし、読みやすい。評判に聴くとおり、とても後味の悪い作品。だからこそ、このくらいの読みやすさが必要であるともいえる。
年末に購入していたが、やっと読めた。読みはじめたら一気だった。そのくらい、読ませるし、読みやすい。評判に聴くとおり、とても後味の悪い作品。だからこそ、このくらいの読みやすさが必要であるともいえる。
「聖職者」「殉教者」「慈愛者」「求道者」「信奉者」「伝道者」の6章からなり、各章で視点が変わっていく。最初の章となる「聖職者」は、もともと独立した短編。教師の職を辞する決意をした女性中学教師が、年度末のHRに担任するクラスの生徒たちに語りかける言葉だけで、ひとつの作品となっている。この女教師の幼い娘が、校内のプールで事故死したのだが、それが実は事故ではなく……といった真相が明らかにされていく。第1章のオチがまずズシンとくる。構図から後味から、エルヴェ・ギベールの「ぼくの命を救ってくれなかった友へ」に描きとめられたある光景を想起せずにはいられなかった。
第2章以降は、女教師が去った後日談となり、章を重ねるごとに時間も順方向に流れていく。そして、その中で起こっていく様々なできごとが多視点から幾重にも語られ、できごとの様相が次々と変化していく。各章のタイトルも曲者で、どれもかなりアイロニックである。すべて「毀れた○○者」と読み替えた方が、内容に即しているだろう。といえるほど、主たる登場人物は毀れた人物揃いである。何が毀れているかといえば、ひとくちでいえば、倫理観ということになるだろう。
作品の風合いはまったく異なるが、毀れた人間が、己の生き様を前面に押し立てて疾走していくという感覚という点では「死ぬほどいい女」に通じるものすら感じる。中学校を舞台とした作品で、ジム・トンプスンの作品を想わせる、ってのは、それだけでもすごい。
現実の事件や世間の風潮と照らし合わせてあれこれと深読みしたり、議論したりすることのできる作品だと思うが、ぼくは、これはやはりノワールなんだろうと思う。いくつかの殺人が起こるのに、警察も探偵も一切姿を見せない。暴力や虐めに対して、学校が管理能力を発揮する場面も一切ない。警察や学校の無能が語られることすらなく、ただ単に不在。
その一方で、個人が、それぞれに手前勝手な倫理観や、正義観などを振りかざして、至極自己中心的に切り結び、傷つけあう。これがノワールじゃなくて何だというのか。俺たち悪者だぜ、とあからさまに自己主張する自称悪漢小説なんかより、すべての登場人物が、自分の感覚のまともさを信じて突っ走るこの作品の方が、遙かに背筋を寒くさせる本物のノワールの空気をまとっている。
モダンタイムス
 伊坂幸太郎の新刊。「モーニング」に1年余りにわたって連載されていた作品。あとがきで「ゴールデンスランバー」と同時期に執筆していて重なる部分も多いと著者本人が述懐しているが、確かにそういった面がある。
伊坂幸太郎の新刊。「モーニング」に1年余りにわたって連載されていた作品。あとがきで「ゴールデンスランバー」と同時期に執筆していて重なる部分も多いと著者本人が述懐しているが、確かにそういった面がある。
伊坂幸太郎版「1984」といっていいだろう。そして、大人の小説である、ともいえる。主人公たちは、システムの中で生きることを強いられ、それを諦念とともに受け入れている。システム、すなわち世の中の仕組み、というものを皮膚感覚としてどう感じとっているかによって、この物語の印象は変わりそうな気がする。たとえば中高生であっても、そうしたシステムの何ともしがたい様相を感じとってはいるだろうが、仮にぼくがいま中高生だったとして、この作品を読んだとしたら、印象はかなり異なっていたに違いない。中高生のころにぼくが感じていた閉塞感なんて、所詮保護者の庇護のもとでの甘え、勘違い、思いこみに塗りたくられたものでしかなかったと、いまは思う。二十年前のぼくは反駁するかもしれないが。そして、二十年後のぼくが「モダンタイムス」を読んだら、甘いんじゃないの、と鼻白むかもしれない。実際のところ、そうなるのかどうか知りようはないが、ぼくにとって相変わらず伊坂幸太郎は同世代性を色濃く感じる作家であり、この作品にも、いま出逢えてよかったと感じる。
実家に忘れてきました。何を? 勇気を。
この1行で、小説は始まる。とても伊坂的なすてきな言い回しだが、そこから始まる物語は、読み慣れたポップな伊坂の世界とはちょっと違う。なにせ、冒頭からして、主人公は椅子に縛りつけられて謎の人物に拷問を受けているのだ。
56回にわたって連載された小説は、単行本でもそのまま、56の短い章から成っている。といっても「重力ピエロ」のような断章形式ではなく、ひとつひとつの章が、それなりに起承転結をなしていたりする。マンガ週刊誌での連載という形式が、こうした構成を促したのかもしれない。各章の最後は「次回予告」的なヒキが込められていることも多く、おもしろい。初期の伊坂作品の細かいエピソードがやがてパズルのピースのように組み合わさっていくような構成ではなく、56の章は、基本的に一直線に数珠つなぎとなって全体像をつくる。「オーデュボンの祈り」や「重力ピエロ」にあったような幻惑的なカタルシスはないが、それとは別の、どこかボレロのような繰り返しと変異による昂揚感がある。
動きが生命をつくる—生命と意識への構成論的アプローチ
 タイトルにもなっているダイナミクスこそが生きているということの本質であるという主張には全面的に賛同する。冒頭で語られる中間層の必要性も痛感する。と、すこぶる共鳴して読み進んだが、中盤以降、明らかに文章の質が落ちてしまい、当然、読後感をも損なっている。それでも行間から匂いたつ知の香りは豊かであり、著者の主張を理解したいと心の底から思うのだが、正直、ぼくには理解し尽くせなかった。一読後に著者の論文を渉猟して、理解を進めることができたが、それを要求する書物を「一般向け」とは呼べない。序盤が非常に平易かつ魅力的であるだけに、中盤以降明らかに失速してしまった原因は、筆者の力不足というよりは、執筆や推敲に充分に時間を割くことなく出版してしまったプロセスにあるように思われる。十全に力を注いだ、次の1冊に期待したい。
タイトルにもなっているダイナミクスこそが生きているということの本質であるという主張には全面的に賛同する。冒頭で語られる中間層の必要性も痛感する。と、すこぶる共鳴して読み進んだが、中盤以降、明らかに文章の質が落ちてしまい、当然、読後感をも損なっている。それでも行間から匂いたつ知の香りは豊かであり、著者の主張を理解したいと心の底から思うのだが、正直、ぼくには理解し尽くせなかった。一読後に著者の論文を渉猟して、理解を進めることができたが、それを要求する書物を「一般向け」とは呼べない。序盤が非常に平易かつ魅力的であるだけに、中盤以降明らかに失速してしまった原因は、筆者の力不足というよりは、執筆や推敲に充分に時間を割くことなく出版してしまったプロセスにあるように思われる。十全に力を注いだ、次の1冊に期待したい。
新世界より

 「天使の囀り」にも衝撃を受けましたが、作者の生物学的センスは抜群です。ぼく自身、生命科学の「専門家」の端くれですが、本作に描きだされる想像上の生き物の体系は、ある意味、空前絶後のリアリティを持っていると思います。一方で「呪力」に関する設定は科学的には首を傾げざるをえないものだけに、作者の生き物への執着には畏怖を覚えます。この、少なくとも視覚的には醜悪を極める世界を数年にわたって脳裡に抱きつづけ、ここまでの完成度へと煎じ詰めた精神力は凡人には想像しがたいものがあります。
「天使の囀り」にも衝撃を受けましたが、作者の生物学的センスは抜群です。ぼく自身、生命科学の「専門家」の端くれですが、本作に描きだされる想像上の生き物の体系は、ある意味、空前絶後のリアリティを持っていると思います。一方で「呪力」に関する設定は科学的には首を傾げざるをえないものだけに、作者の生き物への執着には畏怖を覚えます。この、少なくとも視覚的には醜悪を極める世界を数年にわたって脳裡に抱きつづけ、ここまでの完成度へと煎じ詰めた精神力は凡人には想像しがたいものがあります。
物語の詳細に踏み込むのは危険なので触れませんが、読み手の想像力が試される小説です。細かくディテールが描写されているようでいて、視覚的な詳細の描写はストーリーテリング上、最小限描写すべき対象に限られており、それ以外の多くは、世界を構成する要素がいかにしてそこにあるかというプロセス、メカニズムの描写の積み重ねによって提示されています。その結果として、この小説世界に五巻で感じられるどういった光景が展開しているのか、その大部分は読者の想像力に任されています。読み手のそれぞれが、それぞれの経験、想像力に応じて、異なる「新世界」を脳裡に描きだすことでしょう。
近年の日本のエンターテインメント小説の系譜上は、「屍鬼」「シャングリ・ラ」といった流れに連なるものと感じますが、それはストーリー展開の表層を捉えた比較に過ぎないかもしれません。生き物が争い、争いの中で他の生き物を殺すという、ほぼすべての動物種が行っている振る舞いを、詩的ロマンティシズムなどに逸れることなく、真正面から描こうとし、描ききれたかはさておき、完遂したことに敬服します。その中で、生き物が生き物たるがゆえに行う行為の積み重ねの中に、「神」をはじめとする、私たちが「人間らしい」と感じる概念を淡々と畳みこんでみせた点など、唸らされた部分も数多くあります。そして、最後の1行に、さまざまな意味で胸が熱くなりました。傑作です。
したたかな生命
 「システム生物学」という新領域の牽引者・北野宏明さんによる一般向けの書籍というだけで価値がある。20世紀末から北野さんが提唱し論じてきたシステム論的な生命科学やロバストネスから、比較的最近議論しはじめたネットワークの蝶ネクタイ構造まで、「北野理論」とでも呼ぶべき論考のエッセンスがコンパクトにまとまっている。北野さんの考え方にはじめて触れる読者には格好の1冊といえるかもしれない。ただし、これはほんの糸口でしかない。
「システム生物学」という新領域の牽引者・北野宏明さんによる一般向けの書籍というだけで価値がある。20世紀末から北野さんが提唱し論じてきたシステム論的な生命科学やロバストネスから、比較的最近議論しはじめたネットワークの蝶ネクタイ構造まで、「北野理論」とでも呼ぶべき論考のエッセンスがコンパクトにまとまっている。北野さんの考え方にはじめて触れる読者には格好の1冊といえるかもしれない。ただし、これはほんの糸口でしかない。
一方で、書籍としての構成や内容は、ひとことでいってお粗末というレベル。北野、竹内という2名の著者がいるのに、一人称「私」がどちらの視点であるのかがほとんどのセクションで明らかでなく、しかも視点は頻繁に入れ替わっている。北野と竹内ではこの本が語る対象に対する立ち位置がまったく異なるのだから、話者の視点が不明確なのはある程度以上に深い論考を展開する上で致命的だ。
構成も、それぞれのトピックがぶつ切りになって放り出されている感が拭えず、1冊の書籍として俯瞰したときの全体像が曖昧である。それらの結果として、語られている諸概念の表面をなぞることはできても、それ以上に深い考察に触れることはできない。素材の魅力を充分に活かしきれていないという点はかなり残念。