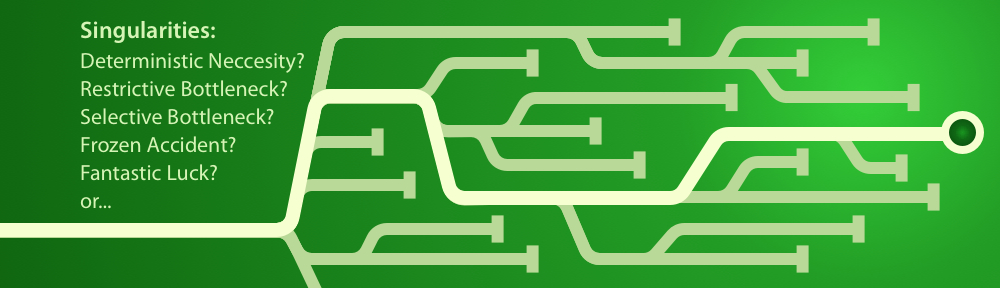(文学の冒険シリーズ) (単行本)
 ポーランドで「虚数」として出版された「架空の書物の序文集」と、後年別に記された「GOLEM XIV」を併せて収録している。両者のリンクとしては、「虚数」の中の一編「ヴェストランド・エクステロペディア」にGOLEMに関する記述があり、またそれ以上に、知性と肉体に関する考察という点で通底している。
ポーランドで「虚数」として出版された「架空の書物の序文集」と、後年別に記された「GOLEM XIV」を併せて収録している。両者のリンクとしては、「虚数」の中の一編「ヴェストランド・エクステロペディア」にGOLEMに関する記述があり、またそれ以上に、知性と肉体に関する考察という点で通底している。
序文集「虚数」は、後半の「GOLEM XIV」への程よいイントロダクションになっている。「虚数」の各編は、様々な衒学的脱線であふれかえっているが、そのすべてにおいて、知性と肉体について言及している。そこから立ち上がってくる問いは、知性は、人間の肉体という仕様に依存する概念なのか、ということだ。肉体、というか人間という物理的存在に拘泥した「ネクロビア」への序文を嚆矢として、その後に展開されるのは、言語を学んだ微生物、機械による文学、コンピュータによる未来予測を編纂した未来百科事典といった、人間以外の知性を題材とした弾けとんだ話だ。
そして、人間が造りだした、人間以上の知性を持つコンピュータ「GOLEM XIV」による人間への講義録の形式を取る「GOLEM XIV」。この中で、GOLEMは、人間について語り、自己について語り、知性について語る。その全貌は到底把握しきれないが、根本にあるアイディアの手触り、手応えは圧倒的。
以下、ぼくの個人的解釈になるが、「知性」は、この地球上では「ヒト」という生物種に至って創発されたが、より一般的な「知性」の在りようは、ヒトの生物学的構造や遺伝情報に拘束されるものではない、というのが本書の中核にある主張である。ヒトが持っている生物学的デザインは、高い知性を持つために最適化されたものではなく、より現実的な、生き抜き、殖えるために最適化されてきている。そこに運良く知性が宿り、現在の程度まで到達したが、人間の到達しうる知性は、ヒトの生物学的デザインにどうしようもなく縛られている、というわけだ。そして、人間が造りあげた計算機であるGOLEMは、そのデザインのくびきを断ち切った次世代の知性であり、人間が到達し得ない、理解の及ばないところにまで達している。
これは絶望的であり、なおかつ心揺さぶられる言明である。ぼくは、基本的にはまったくそのとおりだと思う。その上で、人間がもがき回る、人間の知性が探り当てられる知識もまた、事実上無限であり得ると信じられるからだ。限られたハードウェアの上で、エネルギー吸収的に営まれるぼく自身の知性が、いかほどのものを紡ぎだせるのか、落胆よりもむしろ勇気づけられた。どの程度のものであれ、自分にはどうやら知性と呼べるものが備わっていることに感謝したいし、そのポテンシャルをフルに引き出してみたいと思う。
レム亡きいま、知性に関する思索を文字通り「空前絶後」の完成度で示した本書に及ぶものはおろか、類似する文学作品すら、今後産まれる望みはないように思える。
Amazon Review
 「A Genetic Switch」第3版の邦訳。第2版は「絵とき 遺伝子スイッチ」(ISBN:427402167X)として邦訳されていて、現在古書として1万円以上の価格で取引されている。学生時代、分子遺伝学の研究室に移ったときに指導してくれた先輩院生から、まず読めと最初に渡されたのが「絵とき 遺伝子スイッチ」で、一晩で読破した。λファージの生活環を通じた遺伝子発現を解説した本なのだが、一般的に遺伝子発現調節について理解すべき事柄のエッセンスがλファージの生物学にみごとに詰め込まれており、分子生物学を学ぶための端緒としてかなりオススメな1冊。
「A Genetic Switch」第3版の邦訳。第2版は「絵とき 遺伝子スイッチ」(ISBN:427402167X)として邦訳されていて、現在古書として1万円以上の価格で取引されている。学生時代、分子遺伝学の研究室に移ったときに指導してくれた先輩院生から、まず読めと最初に渡されたのが「絵とき 遺伝子スイッチ」で、一晩で読破した。λファージの生活環を通じた遺伝子発現を解説した本なのだが、一般的に遺伝子発現調節について理解すべき事柄のエッセンスがλファージの生物学にみごとに詰め込まれており、分子生物学を学ぶための端緒としてかなりオススメな1冊。