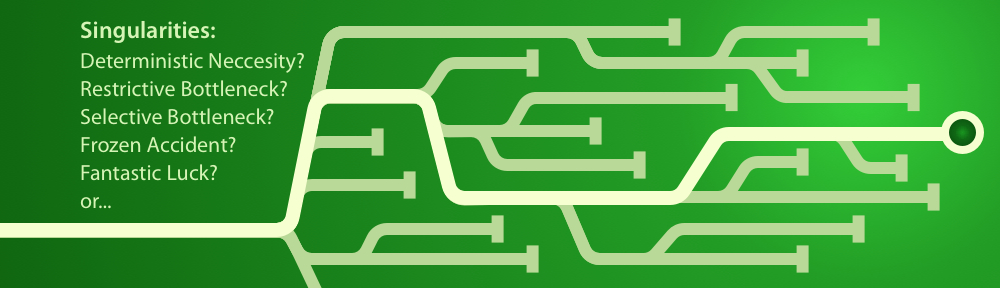東野圭吾は「さまよう刃」あたりから、被害者の視点を強く意識しており、本作もその流れの上にあります。加賀恭一郎というキャラクターは、「どちらかが彼女を殺した」「嘘をもうひとつだけ」など東野作品の中でもロジック重視の作品に起用されてきた印象があります。加賀の特徴は、何気ない会話にひそむ意味を拾いあげながら真相へと詰め寄っていくスタイルにありますが、それはそのままに、新たな東野作品で活躍しているのは、年輪を重ねた俳優が新境地を開拓したようで愉しめます。
東野圭吾は「さまよう刃」あたりから、被害者の視点を強く意識しており、本作もその流れの上にあります。加賀恭一郎というキャラクターは、「どちらかが彼女を殺した」「嘘をもうひとつだけ」など東野作品の中でもロジック重視の作品に起用されてきた印象があります。加賀の特徴は、何気ない会話にひそむ意味を拾いあげながら真相へと詰め寄っていくスタイルにありますが、それはそのままに、新たな東野作品で活躍しているのは、年輪を重ねた俳優が新境地を開拓したようで愉しめます。
本作「麒麟の翼」には、どんでん返しはありません。加賀の捜査によって、初期の印象とはまったく異なった方向へと事件が収束していきますが、いわゆる謎解きの快感や意外性に満ちた物語ではありません。この物語には、理解不能なサイコパス的な登場人物はひとりも登場しません。被害者は死亡し、加害者は逃走中の事故で意識不明の重体、という状況で、被害者の家族、加害者の家族、その周囲の人々が描かれます。マスコミなど「部外者」を自認する者たちの振る舞いが、もっとも下劣で暴力的なものとして描かれているのが印象的です。
加賀は、被害者、加害者それぞれの足取りを追いながら、周辺の人物から丹念に聞き取りをおこない、その言葉の端々から矛盾を拾いあげ、誤解を破り、真相へと近づいていきます。一見なんでもなさそうなできごとや会話の中にささやかな不整合=謎を見出し、解きほぐしていく。その「気づき」のひとつひとつが、とても丁寧に考えられており「名工の技」のようにも感じられます。幕切れ近くにドカンと炸裂する大仕掛けに期待するのではなく、全編に散りばめられたきめ細かい技巧の数々を堪能するのが、本作のミステリとしての楽しみ方のように思います。
終盤、この作品中で、加賀が一度だけ激昂し、ある人物に強い言葉を投げかけます。この社会にありふれている振る舞いが、やがて大きな歪みへと育ち、多くの人々を不幸に陥れることすらあるのだという思いが、その言葉には込められています。
かつて東野圭吾は、ミステリを逸脱するのではなく、拡張したい、自分の書くものはミステリである、のように述べていました。「麒麟の翼」もミステリの構造をとりながら、普遍的な物語へと昇華した小説になっています。